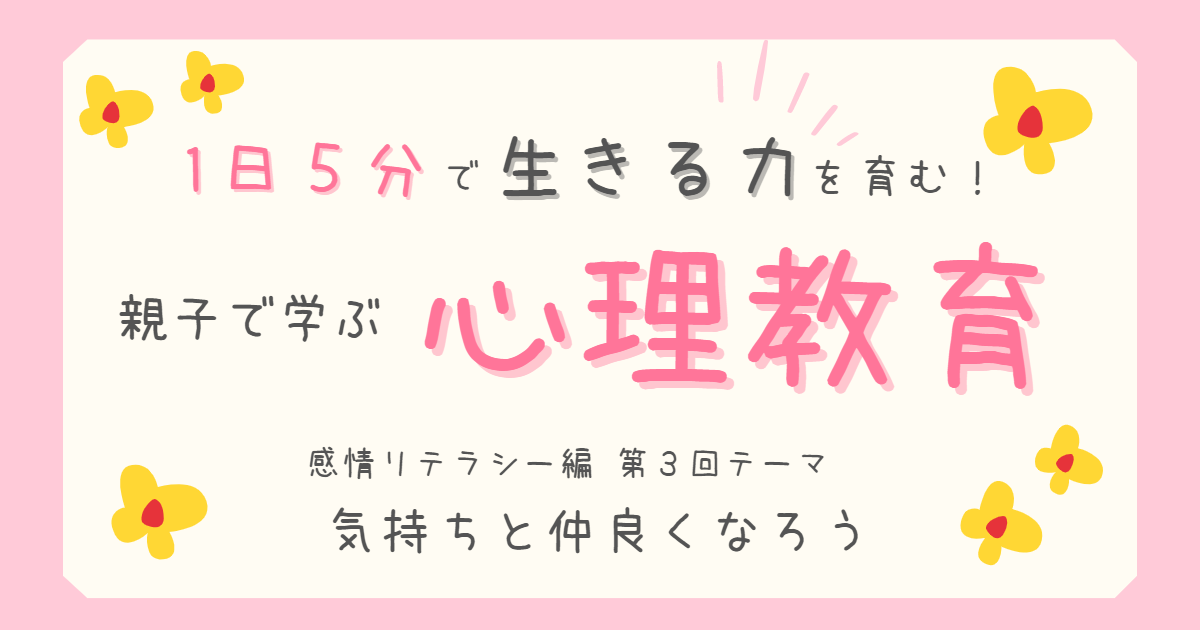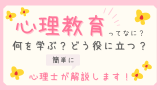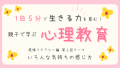こんにちは!こころ先生です(^^)
第3回、「1日5分で!生きる力を育てる親子で学ぶ心理教育」!
「心理教育ってなに?」と気になった人はこちら
おやつの時間のあと、お風呂の時間、寝る前などのゆったりとした親子時間などに、会話をしながら、そして楽しみながら、しかも親子で役に立つ「心の仕組みやスキル」について学べるような内容です!
親子はもちろん、学校での授業(学校だと道徳の授業になるのかな?)でも使えるような内容だと思います♪
インスタグラムでも発信しています!フォローしてくれるとうれしいです♪
Ⅰ.導入:テーマ「気持ちと仲良くなろう」
今回のテーマは、「気持ちと仲良くなろう」です。
ポジティブな「気持ち」も、ネガティブな「気持ち」も、どんな「気持ち」もあなたにとって大切な「気持ち」であるということを学ぶことが今回のテーマの目的です。
- 感情のコントロールが難しい
- 癇癪、人や物を叩くことが多い
- 自分や他人の気持ちを考えることが苦手
- 気持ちを言葉にすることが苦手
気持ちには「ポジティブな気持ち」もあれば「ネガティブな気持ち」もあります。
ポジティブな気持ちはたくさん感じたいと思いますが、ネガティブな気持ちはできれば避けたいと思うものです。
もしかしたら、ネガティブな気持ちは「恥ずかしい」と思って見ないようにしたり、誤魔化そうとしたりする人も多いかもしれませんね。
しかし、ネガティブな気持ちを否定することは、心の健康を考えると逆効果。
ネガティブな気持ちにも役割があります。
例えば、「怒り」の感情は、大切なものを守るために必要な行動のエネルギーになります。「怖い」という感情には、危険を察知して身を守る役割があります。「悲しい」という感情は、大切なものを失ったことに気づき、周りの人々との絆を深める役割があると言われています。
このように、ネガティブな気持ちにも役割があり、生きていくために必要な感情たちなのです。
ネガティブな気持ちも感じていい。
今回のワークで、子どもたちが「ポジティブな気持ちもネガティブな気持ちも存在していていい」「自分の心の中にあるネガティブな気持ちにも優しくしてあげよう!」と気づくきっかけができるといいなと思います。
Ⅱ.ワーク:私の心に住むキャラクター

さっそく、ワークをやってみましょう!親子で楽しくできるワークを用意しています♪
★用意するもの:色鉛筆かカラーペン。
…さあ、やってみましょう♪
※ワークで使えるプリントは、こちらからダウンロード(無料)できます♪回答例ものせているので、描き方がわからない場合はそちらを参考にやってみてください!お子さんの年齢に合わせて、印刷して使ってみてね★
質問1:キャラクターが描けません…
回答1:キャラクターを描くのが難しければ、以下の方法でもOK!
- ○や△や□や☆などの形で表現してみる。
- 親子で共同作業で描いてみる(目はママ、口は子ども…など)。
- 素材を用意して福笑いのように作ってみる(目のパーツ、口のパーツ、眉毛のパーツ…など)。
↓イメージがわかなければ、こちらの映画を一緒に鑑賞するのもおすすめ!
ディズニー/ピクサー映画 「インサイド・ヘッド」
質問2:子どもが描いたキャラクターが全部同じ…。
回答2:全部同じキャラクターでも問題ありませんよ♪このワークには答えはないのです。子どもなりに表現できたということに気づき、「描けたね!」と表現を認めることが大切です。もしかしたら、キャラクターの性格やどのキャラクターはどんな場面でよく出てくるのかなど、質問をしてみるとキャラクターごとに違った回答が出てくるかもしれませんね♪
Ⅲ.解説:気持ちを客観視する

さあ、気持ちをキャラクターで表現できましたか?見えない気持ちを「キャラクターにしてみる」というのは、前回の「色で表現する」よりもさらに難しかったかもしれませんね。
参考に、私が描いた例をあげますね!
ここでは言葉で書いていますが、実際にどんな絵か見てみたい人は、ワーク用プリント(無料)をダウンロードして見てください♪
- うれしい…名前は「るんるん」。ピンクのハートの形で手足がよく動く。いつもスキップをしていていつもニコニコしている。
- かなしい…名前は「しくしく」。水色の身体に、青い長髪が流れるように垂れている。よく涙を流している。なんでも悪いほうに考える心配性な性格。
- イライラ…名前は「とげとげ」。赤くてとげとげした身体。目がつりあがっている。すぐ熱くなる。理想が高い。最近よく会うような気がする。
- いやだ…名前は「いやいや」。紫の身体で、内巻きにくるくる巻いた耳と手。なんでも「いや!」という。自信がないときに出てくる。
- こわい…名前は「ぶるぶる」。緑色で、耳が大きすぎて顔が隠れている。いつも部屋の隅っこで震えている。
あなたはどんなキャラクターを描きましたか?私が描いたキャラクターと似ているところはありますか?違っているところはありますか?
共通点や異なる点を親子で話し合ってみると様々な気づきが得られると思います。
キャラクターの表情(目・眉・鼻・口の形)、色、体格、ポーズ、さらにはキャラクターの性格、そのキャラクターが好きなもの・嫌いなもの、どんな場面でよく出てきて、キャラクターにどのように接してあげると落ち着くのか…など、キャラクターを描くことで、自分の心の中にある気持ちが可視化されていきます。
気持ちが「キャラクター」によって可視化されると、自分の気持ちについて客観的に眺めることができます。
また、ネガティブな気持ちをキャラクター化することで親近感がわくので、ネガティブな気持ちについても話題にしやすくなります。
もしかしたら、ネガティブな気持ちのキャラクターを「この子、嫌い」「いない方がいい」などと言う子もいるかもしれません。
そんなときは、「○○ちゃんは、そう思うんだね」と気持ちを受け止めつつ、「ネガティブな気持ちにも役割があること」、「どの気持ちも生きていく上で大切な気持ちであること」、「これらの気持ちみんながそろっているからこそ、あなたの心が健康であること」「ネガティブな気持ちも感じていいこと」をぜひ伝えてあげてくださいね。
生活での応用編:気持ちをキャラクター化して話す

「ワークをやってみたいけど、子どもと一緒にやる時間がなかなか取れない…」という親御さんのために、今回も普段の生活の中で、ワークの要素を取り入れた声かけや関わりを考えてみました!
今回のワークの要素を普段の生活の中で簡単に取り入れる方法。
それは… 「気持ちをキャラクター化して話す」です!
「○○ちゃんの【よろこび】さん、元気いっぱいだね!」
「【イライラ】くんがやってきた…!」
「【いやいや】虫を追い出すぞー!」
このように、気持ちをキャラクター化して話してみると、お子さんは自分の感じている気持ちに意識を向けやすくなります。気持ちをキャラクター化することで親近感もわくので、お話に耳を傾けてくれやすいです。
そして、重要なポイントは、ネガティブな気持ちのキャラクターを悪者扱いしないこと!!間違ってもボコボコに退治しないでくださいね!(泣)
「ネガティブな気持ちも大切な気持ち」というところは守りつつ、お話してください。
たとえ、悪者のような姿のキャラクターを描いたとしても、「いたずらしたり、暴走することもあるけど、なんだか憎めないやつだなぁ…」くらいの扱いでお願いします(笑)。
まとめ
第3回の「1日5分で!生きる力を育てる親子で学ぶ心理教育」。
今回のテーマは「気持ちと仲良くなろう」でした。
それでは、内容のまとめです。
1.ポジティブな気持ちもネガティブな気持ちも、どんな気持ちもあなたが感じた大切な気持ち。
2.気持ちを「キャラクター化」することで、
- 自分の気持ちが可視化され、自分の気持ちを客観的に眺めることができる。
- ネガティブな気持ちも「キャラクター化」することで、親近感がわき、ネガティブな気持ちについても話題にしやすくなる。
3.生活の中で、気持ちを「キャラクター化」して話してみることで、子どもは自分や相手の気持ちに意識を向けやすくなる。続けていくうちに、自分の中にある気持ちについての理解が深まっていく。
以上、こころ先生でした!またね♪