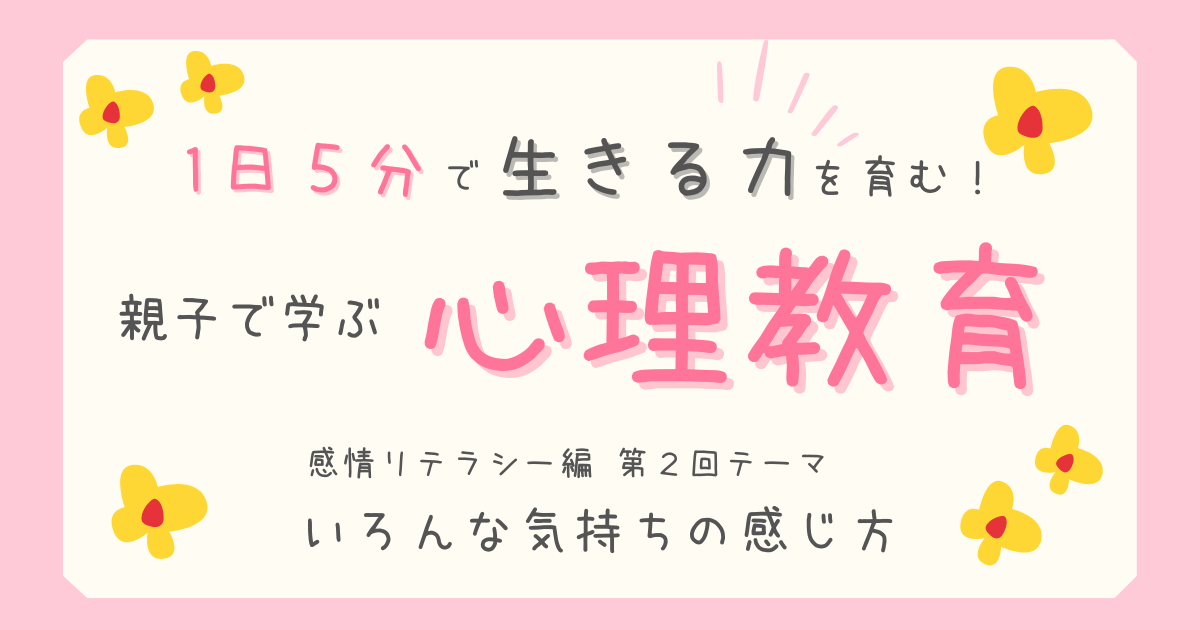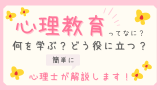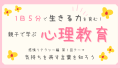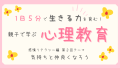こんにちは!こころ先生です(^^)
前回に引き続き、「1日5分で!生きる力を育てる親子で学ぶ心理教育」!
「心理教育ってなに?」と気になった人はこちら
おやつの時間のあと、お風呂の時間、寝る前などのゆったりとした親子時間などに、会話をしながら、そして楽しみながら、しかも親子で役に立つ「心の仕組みやスキル」について学べるような内容です!
親子はもちろん、学校での授業(学校だと道徳の授業になるのかな?)でも使えるような内容だと思います♪
インスタグラムでも発信しています!よかったら遊びに来てね♪
Ⅰ.導入:テーマ「いろんな気持ちの感じ方」
今回のテーマは、「いろんな気持ちの感じ方」です。
「気持ち」は人によってさまざまな感じ方があること、「気持ち」は混ざりあうこともあるということを知ることが今回のテーマの目的です。
- 感情のコントロールが難しい
- 癇癪、人や物を叩くことが多い
- 自分や他人の気持ちを考えることが苦手
気持ちは「色」に似ています。「色」みたいにたくさんの種類があって、絵の具みたいにまざりあうこともあります。
明るい色、暗い色、はっきりした色、ぼんやりした色、ぐちゃぐちゃな色…いろんな「色」があるように、「気持ち」も人によってさまざまな感じ方をします。
ワークを通じて、子どもたちが「自分の気持ちの感じ方と他の人の気持ちの感じ方は違うこともあるのかぁ…」「気持ちってまざりあうこともあるんだ!」「色を使って気持ちを表現する方法もあるんだ!」と気づくきっかけになるといいなと思います。
Ⅱ. ワーク:私の気持ち「絵の具パレット」

さっそく、ワークをやってみましょう!親子で楽しくできるワークをご用意しています♪
★用意するもの:色鉛筆かカラーペン、または折り紙など。(できるだけ多くの色があると◎)
…さあ、やってみましょう♪
※ワークで使えるプリントは、こちらからダウンロード(無料)できます♪今回は、(A)と(B)の2パターン用意しました!お子さんの年齢に合わせて、印刷して使ってみてね★
質問1:なかなか色を選べません…
回答1:答えはないので、好きな色でOK!直感的に感じたものを選びましょう。
あなたが最近感じた「うれしかった場面」を思い出してみましょう。目を閉じてそのときの感情を思い出して、身体の感覚に注意を向けてみて下さい。それを色にたとえてみると何色でしょうか?頭の中に浮かんだ映像にある色でもよいですよ。
質問2:子どもが全部「黒」で塗ってしまいましたが、大丈夫でしょうか?
回答2:大丈夫です!その子なりの表現を否定せず、「表現できた」ことを認めましょう。
「黒なんて…何か心に問題を抱えているのかしら…!?」と心配しなくても大丈夫です(笑)。もしかしたら好きな色(黒)で塗った可能性もあります(笑)
Ⅲ. 解説:気持ちを可視化する

さあ、気持ちを色で表現できましたか?見えない気持ちを色で表現する…感覚的なことなので、「難しかった!」という人もいるかもしれません。
参考までに、私がやってみた例をあげますね。(↓色を載せられなかったので言葉で書いています)
- うれしい…ぼんやりしたやわらかいピンク
- たのしい…明るいオレンジ
- こわい…暗い緑
- かなしい…緑がかった薄い青。ぼんやり滲んだ色
- イライラ…黒っぽい濃い赤
あなたが書いた色と同じでしたか?それとも違う色でしたか?
気持ちの種類によっては、似ている系統の色を選ぶことが多いかもしれませんが、それでも微妙に違ったり、意外な色を選んでいたりしていることもあります。こうやって改めてやってみると、感じ方は人それぞれであることに気付くことができます。この「人それぞれ感じ方がちがうんだ」という部分は、ぜひ子どもたちに気付いてもらいたいポイントです。
気持ちは目に見えないものですが、たしかに感じているものです。特に小さい子どもにとっては、「気持ち」の存在はわかりづらいかもしれませんが、色を使うと表現しやすいようです。
色で表現すると目で見えるので、「今この子はこんな気持ちなんだろうなぁ…」と共有しやすくなります。
今回は「色」を使って可視化をしてみましたが、他にも数字を使ってみたり、動物にたとえてみたりして気持ちを可視化する方法があります。
気持ちを可視化することは、次のような良いことがあります。
■言葉にならない気持ち・複雑な気持ちでも表現しやすく、自分の状態を客観的に理解しやすくなる。
■言葉にならない気持ち・複雑な気持ちでも、自分の気持ちを伝えやすく、相手の気持ちも理解しやすくなる。
気持ちを表現する手段がまた一つ増えましたね♪
まざりあう気持ち…以下のように相反する気持ちを同時に感じることもあります。
- うれしいけど不安
- 緊張するけど楽しみ
- かなしいけどほっとする
こういった気持ちは、なかなか言語化するのが難しいですよね。そんなときに、色を使って表現してみるといいかも!
生活での応用編:気持ちを色で聴いてみる
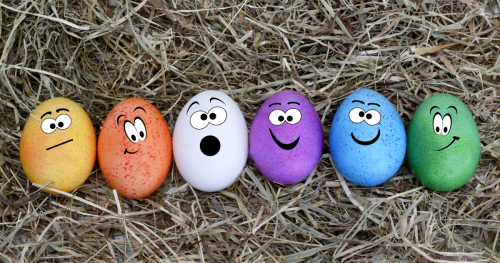
「ワークをやってみたいけど、子どもと一緒にやる時間がなかなか取れない…」という親御さんのために、今回も普段の生活の中で、ワークの要素を取り入れた声かけや関わりを考えてみました!
今回のワークの要素を普段の生活の中で簡単に取り入れる方法。
それは… 「気持ちを色で聴いてみる」です!
「今の気持ち(気分)は色であらわすと何色?」
「ママは今こんな色の気持ちだよ。あなたは?」
「いろんな色(気持ち)がぐちゃぐちゃにまざりあってるみたいだね」
このように、気持ちをうまく言葉で表現できないときは、色鉛筆や折り紙を持ってきて、今の自分の気持ち(気分)に当てはまる色を選ばせてみたり、紙に好きなように色を塗ってもらったりして、今感じているであろう複雑な気持ちを表現してもらいましょう。
モヤモヤした気持ちを表現することで、すっきりするし、あとで客観的に眺めながら話し合うこともできます。気持ちを色で可視化することで、気持ちを扱いやすく、気持ちの整理がしやすくなります。
そして、表現した気持ちは否定せずに受け止めることが大切です。
「あなたはそんな気持ちを感じたんだね」と受け止めてください。
自分の感じた気持ちを表現し、周りの大人が受け止めることで、子どもは「気持ちを表現してもいいんだ」「自分の気持ちは大切にされている」と感じることができます。その土台が積みあがると、他人の気持ちも尊重することができるようになります。
まとめ
第2回となる「1日5分で!生きる力を育てる親子で学ぶ心理教育」。
今回のテーマは「いろんな気持ちの感じ方」でした。
それでは、内容のまとめです。
1.気持ちには人によってさまざまな感じ方があり、気持ちはまざりあうこともある。
2.感じた気持ちを「色」で可視化すると、
- 言葉にならない・複雑な気持ちでも表現しやすく、自分の状態を客観的に理解しやすくなる。
- 言葉にならない・複雑な気持ちでも自分の気持ちを伝えやすく、相手の気持ちも理解しやすくなる。
3.生活の中で、子どもの気持ちの表現を認めていくことで、子どもは「大切にされている」と感じ、気持ちを表現することに自信を持つことができる。その土台ができると、他人の気持ちも大切にできるようになる。
以上、こころ先生でした!またね♪