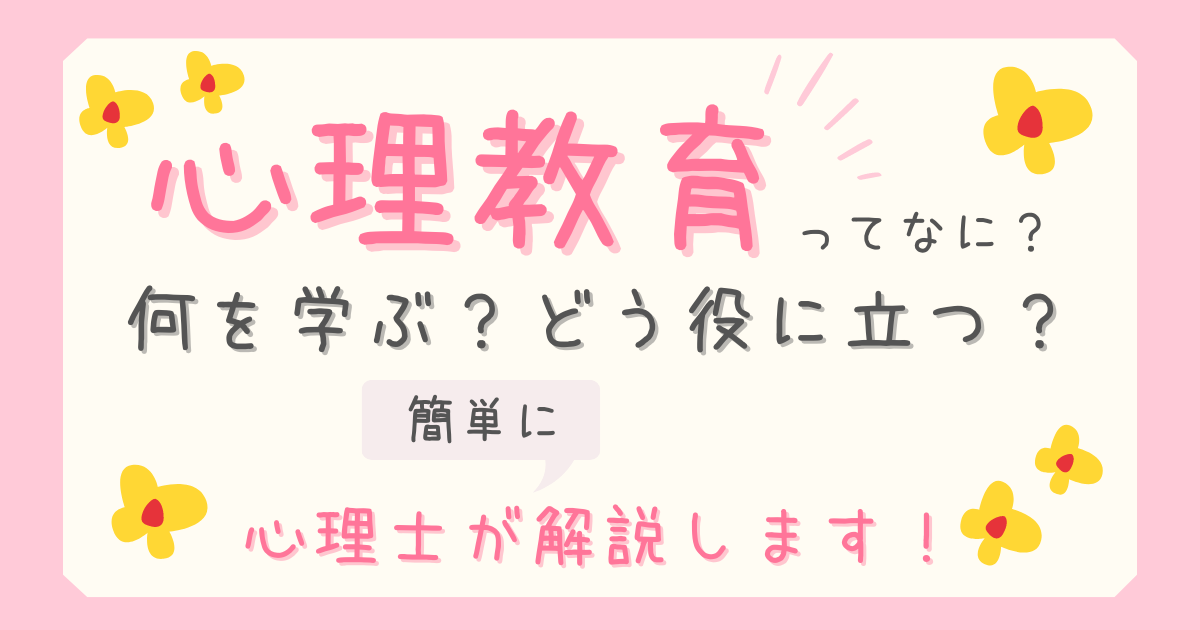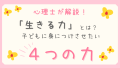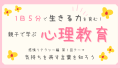こんにちは!こころ先生です(^^)
突然ですが、「心理教育」って聞いたことありますか?
ほとんどの方は知らないのではないかと思います。
「心の教育?なんか怪しい…!」「何かの洗脳?こわくない!?」…などと、思われた方も中にはいるかもしれません。
いえいえ!全く怪しいものではありません!!(←逆に怪しい?笑)
前の記事でも少し書いたのですが、アメリカの教育現場では心理教育の一種ともいえる「SEL教育」が最近のトレンドで、有用性も認められていることから、日本でもこれから学校教育の中に導入されるようになるのではないかと思います。
そこで今回は、「心理教育」の内容や魅力などについて語ろうと思います!
この記事を読むことで、一人でも多くの人が「心理教育」の大切さに気付き、興味を持ってもらえたらうれしいです!
心理教育ってなに?

「心理教育」とは、心に関する知識を学んだり、必要なスキルを身につけることで、さまざまな心の問題や病気を予防し、心の健康を保つために行う教育のことです。
一言でいうと、「心の健康のための予防的教育」といえます。
身近な例でいえば、「未成年の薬物・アルコール乱用防止のために、薬物やアルコール、についての知識を学び、誘われた時の断り方を知る」ことは、予防的な心理教育といえます。
さらに他の例でいえば、「うつ病の予防のために、ストレスについての知識を学び、ストレスへの対処やコントロールの方法を知る」ことも、予防的な心理教育といえます。
心理教育が行われる対象や場所は?

実施するプログラムの内容にもよりますが、基本的には子どもから大人まで幅広い年齢を対象に行うことができます。
個人はもちろん、少人数グループや大きなグループに対しても実施されています。
場所は、病院、学校、療育施設、職場など、さまざまところで行われています。
病院では・・・うつ病や統合失調症、アルコール依存症や薬物依存症などの患者さんやその家族を対象に、少人数のグループでワークや話し合いを通じて病気の理解を深めたり、対処法を学んだりする。
学校では・・・クラスや学年を対象に、少人数グループに分けて、テーマについて話し合ったり交流したりしながら、知識や対処法などを学ぶ。
療育施設では・・・障害を持つ人やその家族を対象に、障害についての知識を学んだり、生活の中の困りごとをテーマに取り上げて、よりよい対処法などを話し合ったりする。
※ここから先であつかう「心理教育」は、主に学校教育の分野での実施を想定して書いています。
心理教育を受けるとどう役に立つ?

アメリカの学校教育のトレンドである「SEL(※社会性と情動の学習:心理教育プログラムの総称)」の研究によると、社会性や感情に関するスキルの向上、問題行動の減少、出席率の向上、生徒指導の問題の大幅な減少、さらには学力(認知能力)の向上にもつながったという結果が得られており、教育の有効性が認められています。
日本の教育現場での心理教育の実施例としては、抑うつに関する心理教育を小学生(佐藤ら,2009)や女子大生(亀山ら,2015)に実施した研究があり、抑うつ症状の減少、社会的スキルの向上、ネガティブな認知の減少、学校不適応感の減少の他、抑うつ対処への自己効力感(抑うつにうまく対処できるという自信)の向上、周囲へのサポート期待の向上など、それぞれ研究で有効性が示されています。
また、中学生を対象にいじめ抑制を目的とした心理教育的プログラムを実施した研究(中村ら,2014)では、いじめ停止行動に対する自己効力感(自分は目の前で起こっているいじめを止めることができるという自信)の向上、いじめ否定の規範意識(いじめは良くないという意識)の向上、いじめ加害傾向の減少などの可能性が示されています。
心理教育ではどんなことを学ぶの?

どんな対象者、何を目的とするのかによって、学ぶ内容は様々です。
一般的な内容としては、以下のようなものがあります。
- 感情の自己理解・他者理解
- 感情コントロール(アンガーマネジメントなど)
- ストレスマネジメント
- リラクセーション法
- ソーシャルスキルトレーニング(SST:社会生活技能訓練)
- アサーショントレーニング(自己主張訓練)
- 心の病気についての知識と予防
- 事故や災害時のストレス対処 …など
生活の中で起こりうる問題への対処法などを学ぶことが多いです。
心理教育はどんな流れで行うの?

これも、プログラムによりますが、大体は以下のような流れで行うことが多いです。
- 導入:テーマと目的を説明することで、参加者の動機付けをします。参加者が見通しをもって参加することができるようにします。
- ワークの実施:テーマについて考え、話し合います。ロールプレイをしたり、プリントに書き込んだりしながら学びます。参加者同士の交流の中での体験から、気づきを促すことを目指します。
- 振り返り:最後に話し合った内容を共有したり、テーマについてのまとめをわかりやすい言葉で参加者に伝えます。
また、心理教育を行う上での注意点があります。
これらは、心理教育を実施する前に「約束事」として周知しておく必要があります。
- 否定しない。肯定的に受け止める・・・相手の意見を否定したり、けなしたり、悪口を言わないこと。答えが一つではないテーマを扱うことが多いので、さまざまな感じ方や考えがあることを理解し、相手の発言を尊重すること。
- 強制しない、無理させない・・・言いたくないことは言わない、参加したくないときは無理しないでよいこと。楽しく参加できるようにすること。
まとめ

「心理教育って心の健康のために役に立つのか~」「もっと知りたくなってきた!」「私も学んでみたい!」…と少しでも興味を持ってもらえたでしょうか?
本当なら、学校で時間をとって実施してもいいくらい価値のある教育だと私は思うのですが、実施する時間や人材の確保が難しいのか、日本の教育現場ではまだあまり導入が進んでいないのが現状です。
最近では、心理教育の大切さに気付き、プログラムを導入し始めている学校も少しずつ出てきてはいますが、多くの学校ではほとんど実施されていません。あったとしても、単発で少し実施するくらいだと思います。
もし余裕のあるスクールカウンセラーさんいたら、ぜひ導入を!!笑
(学校の先生方への説明、理解・協力を得るという高いハードルがありますが…)
「心」というのは目に見えない物なので、どうしても後回しになりがちです。
気づかぬうちに無理をしすぎて体を壊してしまって、病気になって初めて気づく…ということが起こってしまいます。
目に見えないからこそ、時々振り返って考えたり、早めに気づいてケアしたりすることが大切です。
身体の病気や虫歯になったときに、治療のために何回も病院に通わないといけなくなるのと同じで、心に問題を抱えた時も、そこから回復するためには、何回も面接やセラピーを重ねないといけなくなることが多いです。
身体の病気も、睡眠・食事・運動の見直し、予防接種、定期的な健康診断などの予防が大切。
虫歯も、日ごろの歯磨きや定期的な健診など、予防が大切。
そして、心の健康を保つためにも予防が大切です!
心と身体はつながっていますしね!
この記事をきっかけに、少しでもみなさんに「心の健康」について考えてもらえたらいいなと思います♪
最後に、なぜこの記事を書いたかというと・・・
私(こころ先生)も、子ども・もしくは親子を対象に、
【楽しく学べる心理教育グループ 】を企画中!
ご興味がある方はぜひインスタをフォローしてお待ちを…♪
↓↓↓↓↓
https://www.instagram.com/th.cocoro
あと、お勉強に関する記事や家庭教師探しのコツについてのブログも書いてます♪
家庭教師マニュアル→https://katekyo-text.ltt.jp
以上、こころ先生でした!ではまた♪
【参考文献】
福島・尾久・山蔦・本田・望月(2018)公認心理師必携テキスト 学研
下山・松丸・鴛渕・堤(2013)スクールカウンセラーと教師が協働する実践マニュアル 子どものこころが育つ心理教育授業のつくり方 岩崎学術出版社
佐藤寛・今城知子・戸ヶ崎泰子・石川信一・佐藤容子・佐藤正二(2009)児童の抑うつ症状に対する学級規模の認知行動療法プログラムの有効性 教育心理学研究,57;111-123
亀山晶子・及川恵・坂本真士(2015)女子大学生における抑うつ予防のための改訂版心理教育プログラムの検討 心理学研究,86;577-583
中村玲子・越川房子(2014)中学校におけるいじめ抑制を目的とした心理教育的プログラムの開発とその効果の検討 教育心理学研究,62;129-142