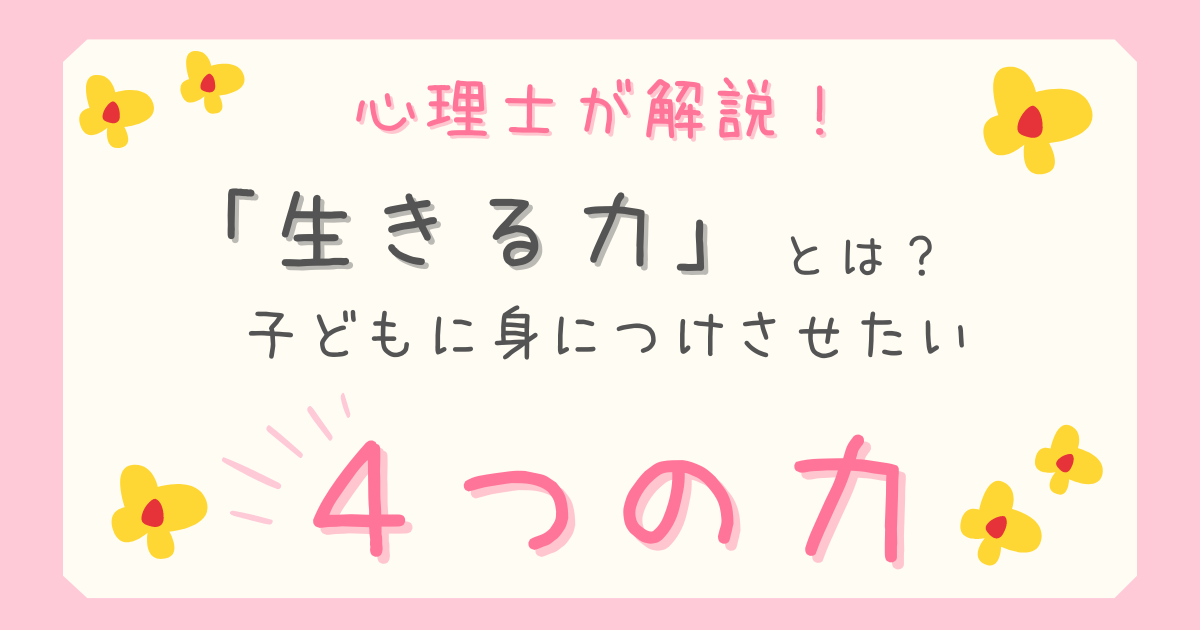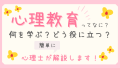- 子どもたちがこれから生きていく時代に不安を感じる。
- 「生きる力」が必要というけど、具体的にどんな力を身につけさせたらいいの?
- 親(先生)として、子どもたちにどんな力を身につけさせたらいい?
こんにちは!こころ先生です(^^)
最近では、やっと少しずつ通常通りの生活に戻りつつある状況ではあるものの、ここ数年は、コロナウイルス感染症の流行、毎年のように起こる大きな地震や洪水などの災害、そして最近では気になるウクライナ情勢…。不安が多く、先行きの読めない時代です。
子どもたちはマスクを常につけて、お友達や先生などの表情もなかなか見られない中での生活。
対人距離を気にしながらの生活、お友達と集まって遊ぶ機会も減り、お出かけも気軽にできない日々…。テレビやネットでは暗いニュースが毎日のように飛び交う。子どもも大人も、世界全体が不安な気持ちやストレスが溜まっている中、なんとかここまで乗り越えてこれましたね…!
しかし、これから先もこうした大変な状況に見舞われることがあるかもしれません。そんな予測不能で厳しい時代の中でも、子どもたちには明るい未来を信じて、強くたくましく生きていってほしい…。
私も含め、ほとんどの親御さんたちはそう願っていることだろうと思います。
「生きる力」
まさに今の時代、子どもたちに身につけさせたい力といえます。2020年度に学習指導要領の内容が見直され、そこでも掲げられているのが「生きる力」。
でも、「生きる力」って具体的にどんな力を指すのでしょうか?
今回は、子どもたちに身につけさせたい「生きる力」について考えてみたいと思います。
日々子どもたちと関わる親や先生が、子どもたちに身につけさせたい「生きる力」について理解し、以下に紹介する4つの力を意識することが、子どもたちの「生きる力」の育成につながるはずです!
※この記事は文章が長くなりましたので、「結論だけ知りたい!」という方は、目次から直接「まとめ」へどうぞ!「どうしてこの4つの力が必要なの?根拠を知りたい!」という方は最初から読んでいただけると嬉しいです♪
関連の深い概念から考える「生きる力」

「生きる力」って言われても、具体的にどんな力のことを指すのか?ぼんやりしていてわかりづらいですよね。
まずは、「生きる力」の定義から考えていきたいと思います。
「生きる力」について語られているものをいくつか取り上げて、整理していきましょう。
- 生きる力(学習指導要領より)
- ライフスキル(WHOより)
- 非認知能力
- SEL(社会性と情動の学習)
それでは、詳しく見ていきましょう!
1.生きる力(学習指導要領より)
まず、押さえておきたいのが、学習指導要領の理念として掲げられている「生きる力」。
学習指導要領とは、全国どこの学校でも一定の水準が保てるよう、文部科学省が定める教育課程(カリキュラム)の基準です。およそ10年に1度、改訂しています。子どもたちの教科書や時間割は、これを基に作られています。(文部科学省HPより引用)
学習指導要領の歴史を振り返ってみると、1998年度の学習指導要領から、「生きる力」の育成を理念として掲げており、現在の学習指導要領(2020年度改訂)でもこの理念は継承されています。
この「生きる力」の育成を目指し、社会に出てからも学校で学んだことを生かせるよう、現在の学習指導要領では、以下の3つの力をバランスよく育むことを目標としています。
- 学んだことを人生や社会で生かそうとする「学び向かう力、人間性など」
- 実際の社会や生活で生きて働く「知識及び技能」
- 未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力」
この「生きる力」を育むために、授業では「主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)」の視点を取り入れるようになりました。
また、学校だけでなく、家庭や地域も含め、社会全体で「生きる力」の育成に取り組むことの必要性も述べられています。
つまり、主体的な学びや対話・交流をより重視するようになっているといえます。
2.ライフスキル(WHOより)
次に、「生きる力」に近い概念である「ライフスキル」について。
WHO(世界保健機構)によると、ライフスキルとは、「日常生活の中で生じる様々な問題や要求に対して、建設的かつ効果的に対処するために必要な心理社会的能力」としています。
つまり、「人生をよりよく生きるための技術」ともいえます。
この「ライフスキル」を教えることが、現代社会における子どもたちのさまざまな問題(喫煙、飲酒、薬物乱用、いじめ、暴力、非行、不登校、不安・抑うつ、自殺…など)の未然防止に効果があることがわかってきており、学校教育の中で「ライフスキル教育」を導入し、早い段階から子どもたちに身につけさせるべきであるといわれています。
「ライフスキル」は、以下の10個のスキルで構成されています。
- 自己認識・・・自分自身の性格、長所や弱点などの特性を客観的に理解する力。
- 共感性・・・他者の気持ちを想像し、理解する力。
- 効果的コミュニケーション・・・文化や状況に合ったやり方で、言語的または非言語的に自分を表現する力。
- 対人関係スキル・・・好ましい方法で人と良好な関係を築き、維持することができる力。
- ストレスへの対処・・・生活上のストレス源やその影響を理解し、ストレスのレベルをコントロールする力。
- 批判的思考・・・さまざまな情報や経験を客観的に分析する能力のこと。
- 創造的思考・・・自分の行動や考えがもたらす結果について考える力。
- 情動への対処・・・自分や他者の感情やその影響を理解し、適切に対処する力。
- 意志決定・・・様々な選択肢の中から、生活に関する決定を自分で判断する力。
- 問題解決・・・日常で起こるさまざまな問題を建設的に処理する力。
これらのスキルは、互いに関連しあっており、まとめると以下の5つの領域に分けることができます。
- 意志決定のスキル(意志決定ー問題解決)
- 目標設定のスキル(創造的思考ー批判的思考)
- コミュニケーションのスキル(効果的コミュニケーションー対人関係スキル)
- 自己認識のスキル(自己意識ー共感性)
- ストレスマネジメントのスキル(情動への対処ーストレスへの対処)
3.非認知能力
次に、最近の幼児教育の分野で注目されている「非認知能力」について。
「非認知能力」とは、数値では測りにくい「心の動き」に関する能力のことを指します。
一方で、「認知能力」とは、読み書きや計算などの「テストで数値化できる力」のことを指します。
幼児期から「非認知能力」を伸ばすことが大切であると言われており、「非認知能力」の教育によって、学力などの「認知能力」にも良い影響を与えることが国内外の研究によって明らかにされてきています。
- 誠実性・・・課題にしっかり取り組むパーソナリティ
- グリット・・・困難な目標への情熱と粘り強さ
- 自己制御・自己コントロール・・・目標の達成に向けて自分を律する力
- 好奇心・・・新たな知識や経験を探求する原動力
- 批判的思考・・・情報を適切に読み解き活用する思考力
- 楽観性・・・将来をポジティブにみて柔軟に対処する能力
- 時間的展望・・・過去・現在・未来を関連付けて捉えるスキル
- 情動知能・・・情動を賢く活用する力
- 感情調整・・・感情にうまく対処する能力
- 共感性・・・他者の気持ちを共有し、理解する心理特性
- 自尊感情・・・自分自身を価値ある存在だと思う心
- セルフ・コンパッション・・・自分自身を受け入れて優しい気持ちを向ける力
- マインドフルネス・・・「今ここ」に注意を向けて受け入れる力
- レジリエンス・・・逆境をしなやかに生き延びる力
- エゴ・レジリエンス・・・日常生活のストレスに柔軟に対応する力
たくさん挙げましたが、これらは以下のようにまとめることができます。
- 自己効力感(自分ならできる!と信じる気持ち)
- 動機付け(モチベーション、やる気)
- メタ認知方略(自分の考えや行動を客観的に把握・分析し、目標達成のために計画を立てること)
- 社会的スキル(社会の中で人と関わり生活していくために必要な力)
4.SEL(社会性と情動の学習)
「非認知能力」と同様に、最近注目され始めているのが「SEL(社会性と情動の学習)」です。
「SEL(社会性と情動の学習)」は、「子どもや大人が、情動(感情)の理解と管理、積極的な目標設定と達成、他者への思いやりと表出、好ましい関係づくりと維持、責任ある意思決定について、これらを実践するための知識、態度、スキルを身につけて効果的に利用できるようになる過程」(CASEL、2012)と定義されています。
日本ではより簡潔に「自己の捉え方と他者との関わり方を基礎とした、対人関係に関するスキル、態度、価値観を育てる学習」(小泉、2011)と説明されています。
特にアメリカの教育現場では、トレンドとなっており、学校でもSELのプログラムが導入されています。
SELが注目されるようになったきっかけとしては、1960年代に行われたアメリカのイェール大学のプロジェクトがあげられます。プログラムの導入により、社会性や感情に関する能力の向上、問題行動の減少、出席率の向上、生徒指導の問題の激減。さらには学力(認知能力)の向上にもつながったという結果が得られ、教育の有効性が認められています。
日本ではまだ少数ですが、問題の早期解決や予防のためにプログラムを導入している学校も出てきているようです。
「SEL」で育む力は以下の5つです。
- 自己への気づき・・・自分の気持ちや考え、強みや弱み、価値観などを理解し、自信を持って物事に取り組む力。
- 自己のコントロール・・・自分の気持ちや考え、行動、衝動、ストレスなどを適切にコントロールする力。自ら目標を設定し、やる気を維持しながら目標を達成する力。
- 社会・他者への気づき・・・他人の立場を尊重し、他者の立場に立って物事を理解し、共感する力。倫理的・社会的な規範を深く理解する力。
- 対人関係・・・他者と良好な関係を築き、維持・修復したり、協力したりする力。悪い場の空気に流されない力。対立を建設的に解決する力。自分の意見を表現したり、他人の意見を聞ける力。自分から助けを求めたり、他人を助けたりする力。
- 責任ある意思決定・・・倫理的・社会的な規範に沿って、建設的な選択をし、行動することができる力。自分の行動の結果を客観的に評価する力。問題の分析し解決する力。
関連の深い概念から考える「生きる力」のまとめ
ここまで、「生きる力」と関わりの深いと思われる4つの概念を整理して、「生きる力」を考えてきました。
いろいろ難しい話をしてきたので、混乱されている方もいらっしゃるかと思います。(というか、ここまで読んでくれる人はいるのだろうか…?汗)
長くなりましたが、ここで簡単にまとめたいと思います。
- 学習指導要領から考える「生きる力」とは・・・学ぶことに興味関心を持ち、主体的に学び、考え、見通しをもって取り組む力。これま学んだ知識を実際の社会や生活の中で生かす力。対話や交流を通じて考えを広げたり深めたりする力。
- ライフスキルから考える「生きる力」とは・・・自分で考えて判断する力、問題解決力、意思決定力、情報や結果を客観的に分析する力、対人コミュニケーション力、自己の理解と相手の理解、感情やストレスをコントロールする力。
- 非認知能力から考える「生きる力」とは・・・自分はできる!と信じる力、やる気を出したり維持したりする力、客観的に物事を考えて計画を立てる力、社会的スキル。
- SELから考える「生きる力」とは・・・自己理解力、自信を持って物事に取り組む力、ストレス・感情・行動などをコントロールする力、他者の視点に立って物事を考える力、対人コミュニケーション力、自己決定力、客観的かつ冷静に問題を分析したり解決する力。
4つの概念から共通している力をざっくりまとめると、以下のようになります。
- 自己理解力、自分で客観的に物事を思考・判断・分析・解決する力
- 自信をもって物事に取り組む力
- 自分の感情・ストレス・行動をコントロールする力
- 他者の視点から物事を考え・理解する力、
- 社会的スキル(対人コミュニケーションを含む)
「生きる力」の大枠が少し見えてきましたね!
心理士の経験から考える「生きる力」

ここからは、私の経験から「生きる力」を考えていきたいと思います。
私が、悩みや問題を抱えた子どもたちと関わってきた中で、多くの子どもたちに共通しているなぁと感じていたことがいくつかありました。
それは以下の通りです。
- 他人の気持ちを考える視点を持つことが苦手。そのため人間関係でつまづきやすい。
- 気持ちのコントロールが苦手。
- 自分の軸がなく、他人の評価や意見に振り回される。
- 問題解決の方法はわかっていても、なかなか動けない。やる気が出ない。
そしてこれらは、悩み多き人生を送ってきた私がこれまでの人生で壁にぶつかり、それを乗り越えてきた経験からも共通して言えることでした。
結論:「生きる力」とは、この4つの力を育てること!

そして、私が考える「生きる力」の結論はこちらです!
- 自己を理解する力
- 他者を理解する力
- 対人コミュニケーション力
- 実行・行動力
では、ひとつずつ解説していきます。
1.「自己を理解する力」がなぜ生きる力につながるのか
人の悩みを聴いてきた中でも感じてきたことですが、人間は「自分が本当はどうしたいのか」を見失っている場合に悩むことが多いような気がします。いわゆる「自分の軸」がブレている状態のときに悩んでいることが多いなというのが私の実感です。
カウンセリングって究極なところ、これをやっているんじゃないかなって思っています。
カウンセラーと話をしながら、自分の本当の気持ちに気付いていく作業。
そして、やっかいなことに、「自分のことなのに自分の本当の気持ちがわからない」ことも多いです。というか、悩んでいる段階ではほとんどかもしれません。
親から言われてきたことや、学校や社会の中での価値観などに縛られて、見失っていることが多くあります。
自分がどう感じ、どう考え、どんな気持ちになるのか…など、自分の心の声に耳を澄ますことは、とても大切なことなのです。
特に現在はインターネットやSNSなどの普及で、他者の意見や価値観にいつでもアクセスできる時代。簡単に他者の意見に振り回されたり、自分よりできる人は上に限りなくいたり、ますます自分に自信が持ちづらくなっています。
将来、仕事をしていく上でも、これからの時代は自分の強みを生かして戦っていかなければなりません。自分の強みを知っている人間は、ビジネスにおいても成功していることが多いです。
これからは単純作業はロボットやAIで代用されていく時代。
だからこそ、自分がどんな人間なのか、自分の得意なことや苦手なこと、どんなことが好きでどんなことが嫌いなのか、どんな状況でどう感じ、どう考え、どう行動するのか…自分を見つめ、自分を理解する力が大切です。
2.「他者を理解する力」がなぜ生きる力につながるのか
自己理解が進み、自分の考えや意見をしっかり持っていることは大切ですが、だからといって周りのことを全く考えず、何事も自分のことしか考えることができない人間は、周りから嫌がられますよね。周りから避けられたり、場合によっては攻撃されたりすることもあり、人とコミュニケーションをとることが難しくなってしまいます。
他人の気持ちを推測する力は、対人コミュニケーションの基礎にもなります。
相手がどういう状況にいて、どんなことを考えていて、どんな気持ちを感じているのか。それらを汲み取ることで、どんな声をかけるといいのか、相手のことも考えた上で行動しなければなりません。
また、他者を理解することは、ビジネスを行う上でも重要です。相手が喜ぶことを考えることで、必要なサービスや商品が生まれてきます。相手視点をもつことができる人は、仕事上でも役に立ちます。
3.「対人コミュニケーション力」がなぜ生きる力につながるのか
「自己を理解する力」と「他者を理解する力」。その力が身についたとしても、実際に自分の気持ちを上手に伝えたり、相手の気持ちをくみ取って適切な行動をとる方法を知らなければ、うまく相手とコミュニケーションは取れません。
実際に人とうまく関わるためには、コミュニケーションをとる力が必要です。
人間は、人と関わらないと生きていけない生き物です。最近では、「一人の方が気が楽だし、一人の方が楽しい。一人でも生きていける!」という人も増えてきた印象にありますが、例えば「無人島に一人で死ぬまで生活することができるか?」と考えれば、多くの人にとってそれはつらいことでしょう。
最近では、コロナ禍でしばらく人と会う機会を制限されたこともあり、ますます人とのコミュニケーションの大切さに気付かされた方も多かったのではないでしょうか。
しかし、人と関わることで悩みが生まれることは多くあります。心理学者のアルフレッド・アドラー(1870~1937)も「すべての悩みは対人関係の課題である」と述べているくらい、人間の悩みの多くは「人間関係」にまつわることといっても過言ではありません。
苦手な人と無理して付き合う必要はありませんが、苦手だからといって避け続けたり、縁を切っていく方法しか知らなければ、最終的に転職や引っ越しを続けたり、引きこもり続けたりするしかなく、本人にとっても周りにとっても良い状況とはいえません。
自分も相手も大切にしつつ、円滑なコミュニケーションをとる方法を知っていると、家庭の中ではもちろん、学校、社会に出てからも役に立ちます。
4.「実行・行動力」がなぜ生きる力につながるのか
頭の中で理解していても、なかなか行動できないと悩む方も多いのではないでしょうか(私もその一人です…笑)。
知識ばかりあっても、行動にうつせなければ何も変わりません。たくさん勉強して知識は増えても、それを生かすことができなければ、ただの「知識」のままです。
例えば、飛行機だって、「こういうのがあるといいな…」と思っていた人は何人もいたでしょう。しかし、それを実際に作ろうと考え、何度も失敗を乗り越え作り続けてきた結果、現代に飛行機が存在しています。
スマートフォンだって、「こういうのがあったら便利かも…」とアイデアを思いついた人はたくさんいたと思います。そこから、実際に作ろうと行動にうつした人がいたから、スマートフォンが完成したのです。
アイディアだけでなく、目標や計画についても同じです。目標や計画を立てただけでは、現状は何も変わりません(気分は上がるかもしれませんが…)。目標は目標のまま、計画は計画のままです。それを実際に実行することに意味があります。(まさに自分のことで耳が痛い…笑)
また、目標や計画が特になかったとしても、「とりあえずやってみる」というような行動力も含まれます。行動していくうちに良いアイデアが浮かんでくることもあるからです。
人生において、壁にぶつかることは多々あります。いざというときに行動にうつせる力があると、問題を解決するために行動したり、行き詰った状況に変化を起こしたりすることができるのです。
これら4つの力は相互的に関係しあっている
以上、ここまで4つの「生きる力」について述べましたが、これらは完全に独立した力ではなく、相互的に関係しあっているものだと考えられます。
自分についての理解が進み、自分の長所や短所を理解し受け入れることができると、周りの人との違いや長所短所にも共感し、受け入れられるようになります。つまり、自分を理解する力が育つと、他者の立場を想像し、共感したり理解する力(=他者を理解する力)が育ちます。
そして、「自己を理解する力」と「他者を理解する力」が身についてくると、人とコミュニケーションをとりやすくなり、やりとりの経験を積むことで「コミュニケーションの力」も育ちます。
また、自分という人間をよく理解し、自分を信じる力が育っていると、実際に行動にうつす勇気やモチベーションが湧き、行動にうつすことができます(=実行・行動力)。
「自己を理解する力」「他者を理解する力」「対人コミュニケーション力」「実行・行動力」
これら1つだけ身につければよいのではなく、バランスよく身につけていく必要がありそうですね。
まとめ
今回は、「生きる力」とは具体的にどんな力なのかを考えてみました。
これまで見てきた4つの概念(学習指導要領・ライフスキル・非認知能力・SEL)と、私の経験から考える「生きる力」をまとめると、以下のようになります。
「生きる力って具体的になに?」の結論は以下の4つ!
- 「自己を理解する力」…自分の長所や短所、気持ちや考え、価値観を理解し、受け入れる力。自己コントロール力(感情、衝動、ストレスなど)。情報や経験から物事を客観的・総合的に分析・判断する力。
- 「他者を理解する力」…他者の視点に立って物事を理解し、他者の気持ちに共感する力。他人を思いやる心、倫理的社会的な規範の深い理解。
- 「対人コミュニケーション力」…他者と適切な方法で良好な関係を築き、維持・修復したり、協力したりする力。自分の意見を表現したり、他人の意見を聞ける。自分から助けを求めたり、他人を助けたりする力。
- 「実行・行動力」…自ら課題を見つけ、情熱を持ち、主体的に粘り強く問題に取り組む力。
これら4つの力を意識して身につけていけるように、普段から子どもたちと関わっていきたいですね♪
以上、こころ先生でした。それでは、また!
【参考・引用文献】
文部科学省HP 学習指導要領「生きる力」
小塩真司(2021)非認知能力 概念・測定と教育の可能性
Collaborative for Academic,social,and Emotional Learning.(2012).2013 CASEL guide:Effective social and emotional learning programs,preschool and elementary school edition.Chicago,IL;Collaborative for Academic,Social,and Emotional Learning.
古泉令三(2011)子どもの人間関係能力を育てるSEL-8S 1 ー社会性と情動の学習<SEL-8S>の導入と実践ー ミネルヴァ書房